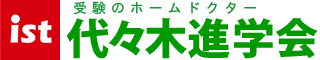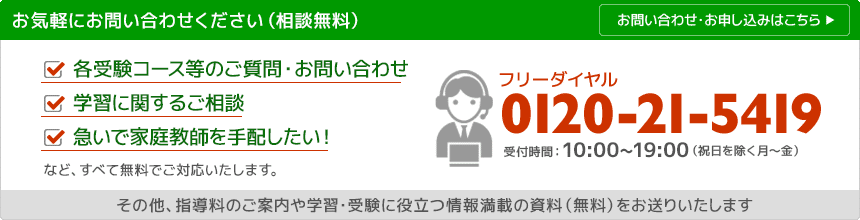中学受験社会の視点から学ぶ紙幣(日本銀行券)のデザイン変更
2019年(2020年入試)は時事問題の当たり年になりそうです。すでに予想の範疇にあるのは「新元号と皇位の継承」「2020年東京オリンピック」「はやぶさⅡの成功」「参議院議員通常選挙」など。これだけでもかなりの知識量を必要とする内容なのに、今はまだ4月をすぎたばかりです。これからどのような出来事が起きるのか、また、それらについてどう教えていくのか、考えると気の遠くなりそうな話ですが、確実に言えることは、こういう年は対応を早めに取らなくてはならないということです。10月になって、各塾の予想問題集が出そろってからでは遅すぎます。
今回取り上げるのは、2024年に発行される新紙幣についてです。各紙幣に印刷される人物が次のように変わります。

◇1,000円札 現行:野口英世 ⇒ 北里柴三郎
◇5,000円札 現行:樋口一葉 ⇒ 津田梅子
◇10,000円札 現行:福沢諭吉 ⇒ 渋沢栄一
1,000円は医学者、5,000円は女性、10,000円は経済に関係が深い人物という構図が変わらないことにはむしろ驚きました。ただの偶然なのかもしれませんが、そこにはもう少し工夫があっても良かったような気がします。老婆心ではありますが…。
さて、新紙幣に登場する人物はいずれも中学受験社会ではおなじみの人物です。改めて取り上げるまでもないのかもしれませんが、再確認の意味でも、彼らの事績について、中学受験社会の視点から重要と思われることをまとめておきます。
※重要度は◎>○>△の順で示しておきます。
渋沢栄一について知っておくべきこと
- ◎ 出身地は埼玉県深谷市である。
※深谷市は埼玉県の北部にあり、利根川の対岸は自動車工業で有名な群馬県太田市、特産品は「深谷ネギ」。 - ◎ 実家は名主階級の農民であるが、のち徳川慶喜に仕え、武士となる。
※「名主(なぬし・みょうしゅ)」は江戸時代の村役人の一種。村の百姓を代表して藩や代官所との交渉に当たり、名字帯刀が許されていた。関西では「庄屋(しょうや)」と呼ばれた。 - △ 1867年、日本が初めて参加したパリの万国博覧会に幕府より派遣されている。
- ◎ 明治に入ってからは経済官僚として活躍し、国立銀行条例の成立に尽力する。
退官後は第一国立銀行(現在のみずほ銀行)の経営にあたる。 - ◎ 東京海上火災保険(現在の東京海上日動火災保険)・王子製紙、麒麟麦酒(きりんびーる)、サッポロビール、帝国ホテル・田園都市(現在の東急電鉄)、東京証券取引所など近代日本の産業を支えた多くの企業を設立したことから、「日本近代資本主義の父」と呼ばれる。
※東急東横線・目黒線沿線の高級住宅街「田園調布(東京都大田区)」は渋沢の開発した町として有名。 - ○ 社会奉仕活動を熱心に行い、日本赤十字社の設立にも協力したほか、二松学舎、国士舘など多くの学校の設立経営に関わった。
※「日本赤十字社」の前身は1877年の西南戦争で救護に当たった「博愛社」という団体で、1886年、「ジュネーブ条約」に加盟して「国際赤十字」の一員となった。
※「国際赤十字」はスイス人のアンリ=デュナンの提唱で設立された戦傷者の救護や人道支援を主務とする組織。 - △ 中国をめぐる権益争いや日本人移民排斥運動によって関係が悪化していたアメリカとの文化交流のために、アメリカの人形(「青い目の人形」と呼ばれた)と日本の人形の交換を成功させた。
※このような国際親善活動が評価され、渋沢は1926・27年のノーベル平和賞の候補になっている。 - △ 畠山重忠・塙 保己一(はなわ ほきいち)とならび「埼玉三偉人」に数えられている。
※畠山重忠は鎌倉幕府の設立に力のあった御家人。知勇兼備・清廉潔白の武将として知られたが、初代執権・北条時政の謀略によって討たれた。
※塙保己一は江戸化政期の国学者。盲目の身ながら国史・国文学の貴重な資料となる『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』をまとめあげた。
津田梅子について知っておくべきこと
- △ 生地は江戸(現在の新宿区)、父は幕臣。
- ◎ 満6歳のとき、北海道開拓使次官の黒田清隆が企画した女子留学生に選ばれ、1871年、岩倉使節団に随行して渡米する。
※梅子は留学生中最年少。他の留学生としては会津藩出身でのちに「鹿鳴館の花」と呼ばれた山川捨松(結婚後は大山捨松)が有名。
※黒田清隆は薩摩出身の政治家。のち第2代内閣総理大臣となり、明治天皇より「大日本帝国憲法」を授けられる。 - △ アメリカのジョージタウン(現ワシントンDCの一部)で教育を受け、1882年に帰国する。
1889年、再度アメリカに留学して大学で生物学を修めるとともに、師範学校で教授法を身につけて1892年に帰国。 - ◎ 1890年、東京麹町(千代田区)に「女子英学塾」を設立、儒教的な良妻賢母型教育とは一線を画し、自由で進歩的、なおかつハイレベルで実力主義の教育を行う。
「女子英学塾」は「津田英学塾」と改称し、1948年「津田塾女子大学」となる。 - △ 再留学中にアメリカで集めた寄付金をもとに女子の留学制度を整え、送り出された留学生の中からは著名な女子教育家が数多く出ている。
北里柴三郎について知っておくべきこと
- ◎ 出身は熊本県阿蘇郡小国町。実家は代々庄屋を務めていた。
※小国町の主産業は林業。「小国杉」が名高い。 - ◎ 東京医学校(現・東京大学医学部)卒業後、ドイツのベルリン大学に留学、コッホに師事する。
この時代に破傷風の血清療法を開発した。帰国後派遣先の香港でペスト菌を発見している。
※コッホはパスツールと並び「近代細菌学の開祖」とされる人物で、結核菌、コレラ菌などを発見している。 - ○ 1901年、第1回ノーベル賞の医学・生理学部門候補者となるも、受賞できず。
※ノーベル賞は共同研究者のベーリングにのみ与えられた。 - ◎ 学問上の理由で東大医学部と対立し、福沢諭吉の支援によって「伝染病研究所」を設立、所長となる。
「伝染病研究所」が国有とされるときには反発し、私費を投じて「北里研究所」を設立する。
行動を共にした研究所の職員には志賀潔もいた。
また、黄熱病の研究で知られる現行1,000円札の野口英世も、アメリカ留学前には「伝染病研究所」に所属していた。
※志賀潔は赤痢菌の発見者。 - △ 福沢との縁で慶応大学医学科(現・医学部)の設立にも尽力し初代医学科長となっている。