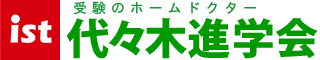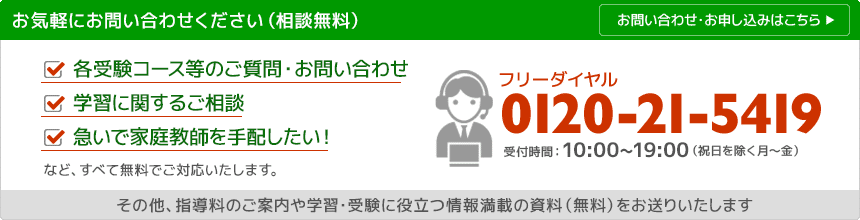数学は重要科目
大学受験にあたり、理系はもちろん文系でも数学必須の難関国立大学や数学を選択できる経済系学部を志望する生徒さんにとって、数学が重要教科であることは間違いないでしょう。
英語同様に積み重ねの教科なので、家を作るように土台からしっかり作っていくイメージが大事です。いきなり屋根だけつけようとしても、風が吹けば簡単に吹き飛んでしまいます。したがって、可能な限り早い段階からしっかり計画的に学習を進めましょう。
皆さんの通われている高校が私立中高一貫校、私立高校、公立高校、あるいは浪人中かによって進捗具合が違うと思いますが、なるべく早く全分野の基礎を固めたいところです。理系の難関大学を志望するなら高2終了時点、他の志望校でも高3夏休みまでには一通り終わらせましょう。
しかし、一人で計画して遂行していくのは、よほど意志が強くないと難しいですし、その計画自体がはたして理にかなっているのかという不安も付きまとうかと思います。
家庭教師と集団塾、個別指導
そこで、家庭教師が各生徒さんの状況と志望大学、学習開始する時期などを総合的に勘案して戦略と学習計画を立てます。
集団塾とは違い、家庭教師は皆さん一人一人に寄り添うことができます。特に受験生は精神的に不安になることもあるかと思いますが、家庭教師は皆さんの良き伴走者として悩み相談や進路相談に乗り、たまには愚痴を聞いてくれる、頼もしく信頼できる存在になってくれるでしょう。
塾では周りに多くの生徒さんがいて悩みなどが言いにくく、このような心理的なサポートまではなかなかおぼつかないのが実情です。
受験において学力はもちろん、精神力もとても大事です。
たとえば模試での判定は一つの目安でしかありません。その結果に対して今何をすべきかを適切にアドバイスしてくれて、最後まで諦めないように励ましてくれるような良き伴走者がいてくれるかどうかは、皆さんの志望大学合格に大きく影響するでしょう。
数学の学習方法
それでは、数学の学習法について詳しくお話しします。
学校の教科書を熟読
近年では新課程に入り、学習内容や単元の分類などが変化しています。まず皆さんに必要なのは、学校の教科書をしっかり理解し、掲載されている問題全てを仕上げることです。
共通テストが導入されてから、会話文などのリード文があったり、パターン化された問題ではなくその場で考察しなければいけないタイプの問題が出題されたりと、より数学的本質を問われるようになっています。
数学も他の教科同様に、教科書を熟読して公式の導き方や定理の証明方法などにも注力したほうが、結果的にスムーズに問題が解けるようになります。
ただ、この部分は独学では限界があります。家庭教師に要点を分かりやすく解説してもらうことで皆さんの数学学習がよりスムーズに進むことは間違いないです。
副教材で基礎力強化
加えて、学校で配布される副教材をしっかり演習することも大事です。『4STEP』や『サクシード』などを繰り返し解くことで基礎体力を身につけましょう。ただし、これらの副教材は解説が不十分という欠点もありますので、『チャート式』や『フォーカスゴールド』などを併用して各分野の理解を深めていくといいでしょう。
家庭教師の指導では『チャート式』や『フォーカスゴールド』の例題の解説を受け、問題を解く際のポイント、公式定理の利用の仕方、注意すべき事項、計算を簡略化する方法などを理解するといいでしょう。
そして宿題で類題の練習問題を解き、学校の副教材で分からなかった問題を次回指導時に質問するなどして、家庭教師をフル活用するのが効果的です。
もちろん生徒さん一人一人の状況によって勉強方法は異なりますので、それぞれに合わせてアドバイスをします。
課題演習の徹底で実力アップ
また、人間は忘れる生き物です。授業で分かったと思っても、放っておくと大部分を忘れてしまいます。
たとえば週1回の授業ならそれ以外の6日間の中で、授業で学んだ分野の類題演習などを徹底することで着実に実力がついていきます。
理想としては、学校授業よりほんの少しでも先に家庭教師に教わると学校授業がより理解でき、問題演習などもスムーズに進み、効率的な学習につながります。
冒頭で、可能な限り早く全分野を終わらせたいとお話ししましたが、現実的には学校の進度より大きく先取りするのはよほど数学が得意な生徒さんでないと難しいと思います。ほんの少し家庭教師で先取りするのが実践的で、志望大学合格への最短ルートになることでしょう。
春・夏休みは既習分野の復習
そして、春休みや夏休みなどに学校授業を遡って、既習分野の復習と演習をすることが重要となります。
たくさんの問題集に手を広げるより、数冊を繰り返し演習することが大学受験においてとても大事になってきます。
有名大学の過去問ではたまに簡単な問題があります。校内テストのように出題範囲が狭いときは解けても、全範囲が出題範囲となる受験本番では、その簡単な問題が難しく見えるものです。ですから、繰り返し演習をして、以前間違えた問題や解くときの悪い癖などを家庭教師に指摘してもらうことで、より一層理解が深まります。
復習のタイミングや復習すべき分野、苦手分野に注力すべきか、志望大学頻出分野に注力すべきかなどは人によって異なりますが、家庭教師がベストな方向に光をあててくれるでしょう。皆さんはその光の方向に全力で走るのみです。残念ながら、一人や集団塾だと暗闇の中にいるようで光がなかなか見えてきません。ぜひ家庭教師とともに足を進めましょう。
夏〜秋にかけては過去問にチャレンジ
このような方法で全範囲の学習が一通り終了したら、高校3年生の夏休みから秋頃に共通テスト過去問や志望大学過去問に一度チャレンジすることをお勧めします。まだスムーズに解けなくても全く問題ありません。一度早めに敵の姿を知ることが大事です。
志望大学が複数ある場合が多いと思いますが、家庭教師が「まずこの大学の何年の問題から解こう」などアドバイスをします。まずはなるべく簡単なところから攻めていきましょう。時間は気にしないで大丈夫です。
入試本番までの日数と現時点でのギャップを図れたら、そのギャップを埋める作業がいよいよ受験数学の勉強です。目指すべき大学の問題の難易度に丁度あった問題集を選択することが非常に大事ですので、プロの出番です。
やみくもに難問題集を解いても実力はつきません。本番の合格ラインが7割なら3割間違えてもいいのです。捨てるべき問題の見極めなども家庭教師にお任せください。皆さん一人ひとりにとって、捨て問題の分野などは異なります。長い時間一緒に走ってきた家庭教師だからこそ、この部分のアドバイスができるのです。
冬休みからは志望校の過去問を時間内に解く練習
そして遅くても冬休み頃からは、共通テストと志望大学の過去問を、時間を計って解きましょう。
時間内に解くことと、速く解きながらも計算ミスやケアレスミスをしないことという、一見相反する事象にどこまで折り合いをつけられるかが勝負のポイントとなります。これは短期間では身につきません。校内テスト直前や模試直前などに家庭教師から「この問題を何分で解こう」といったアドバイスをもらいながら、普段からスピーディーにミスなく解く訓練をすることが大事です。
新しく学ぶ分野の最初の段階では、時間は全く気にしなくて大丈夫です。このあたりのバランスも家庭教師が図ります。
最後はメンタル強化
共通テスト直前は、数学Ⅲの学習は一旦お休みになるかと思います。しかし、一般受験では難関大学になればなるほど、数学Ⅲの比重が大きくなります。ですので、共通テスト終了後はとにかく徹底的に数学Ⅲの微分積分の計算問題を解きましょう。
私立入試と国立入試の間の学習計画なども大事です。最後はメンタルが試されます。
きっと良き伴走者として寄り添ってきた家庭教師だからこそ、この一番大事で一番不安なときに非常に頼りになるでしょう。
そして最後には、一緒に喜びを分かち合う日を迎えることを代々木進学会は切に願っています。