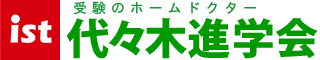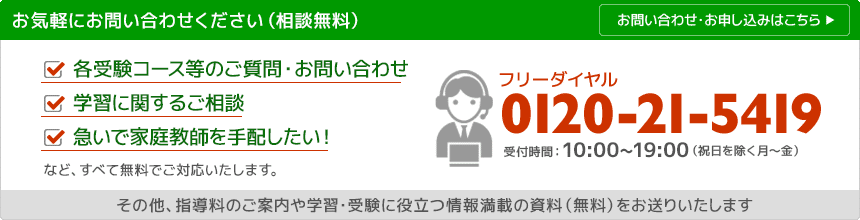大学入試の合否は英語で決まる
大学入試の合否の半分は、英語で決まると言っても過言ではありません。そして、その中で特に配点の高い長文読解(リーディング)を攻略することが大学入試合格に直結します。
習熟度別の学習法
ここでは、習熟度や模試の偏差値別に「いつまでに、何を、どのように勉強すべきなのか」についてお伝えします。①基礎的な読解に不安がある方(模試の偏差値50未満)、②基本的な英文は読めるが、応用的な長文に苦戦している方(模試の偏差値50~60)、③標準的な入試問題の英文は読めるが、難関大学レベルの読解に苦戦している方(模試の偏差値60以上)のそれぞれの場合の学習方法を、ご自身やお子様の現状に合わせてご確認ください。
1 基礎的な読解に不安がある方(模試の偏差値50未満)
基礎的な英文でつまずいている方の多くは、文法と単語の定着がもう一歩ということが多いです。また、文章の分量に圧倒されてしまう方も多いでしょう。そこで、まずは「一文を精確に読めるようにする」ことを目指しましょう。模範解答と一言一句同じ和訳である必要はありません。「事実関係=だれが、どのように、何をしたか」が一致していれば大丈夫です。つまり、「~が」「~を」「~の」などの主語・目的語・修飾関係が合っているということです。
具体的には、『英文読解入門10題ドリル』『英文読解基礎10題ドリル』(いずれも駿台文庫)や『大学入試はじめの英文読解ドリル』(旺文社)を進めましょう。これらの教材は、指示に従い書き込みながら演習することで、基本的な英文の仕組みを定着させながら正しい和訳の力を付けることができます。また、各『10題ドリル』は語句の意味も各ページに記載されているので、「単語が分からないから訳せない」というストレスを感じることも少ないはずです。これらの中から、取り組みやすい教材を進めましょう。自分の書いた和訳が正しいか分からない時は、信頼できる指導者に逐一聞いて、その都度正しい解釈をできるようにしましょう。家庭教師の授業では、反復演習や確認テストの実施によって正しい方法を定着させます。
これらの教材を高1~高2の夏までに定着させましょう。忙しくて高3まで本格的に勉強できなかった方もいると思います。その場合は、高3の夏休みが勝負です。ここで一気に土台を固め、2学期以降の過去問演習に備えましょう。
一文を精確に訳せるようになったら、いよいよ長文読解です。『速読英文(基礎)』(桐原書店)や『全レベル問題集(レベル1)』(旺文社)などを使い、易しめの入試問題に触れていきましょう。進める際は、①問題を解く、②解答解説を確認する、③解説で書かれていることを自分で言語化する(説明する・書き出す)ことで理解を深めましょう。この際、「なぜ自分が間違えたのか」「正しい答えを出すにはどうすればよかったのか」についても言語化すると、次に長文を解く際に正解できる可能性が高くなります。家庭教師の授業であれば、授業内で先生「に」説明することによって理解度を測り、その場で修正することができます。
これらの問題集は高2の冬辺りには解きましょう。高3から基礎→標準、レベル1→レベル2といった形で難易度を上げて志望校のレベルまで進めていきましょう。その都度の学習状況により、進む予定を変えることも大切です。
2 基礎的な英文(教科書レベル)は読めるが、応用的な長文に苦戦している方(模試の偏差値50~60)
この段階の多くの受験生が陥る状況に、「単語は分かっているのに訳せない・単語の意味のつなげ方が分からない」というものがあります。これは「単語の意味をつなげて読む」読み方が原因です。この読み方には、「なぜその訳になるか」という根拠がないからです。ステップアップするためには、「文構造から意味を取る」読み方に変えることが必要です。慣れたやり方を変えるには時間がかかりますから、高2のうちに取り組みたいところです。
そのための教材として、『英文法基礎10題ドリル』(駿台文庫)や『英文解釈の技術100』(桐原書店)といった教材で「文のしくみ」を分析する視点を養いましょう。参考書に記載された「使い方」を参考に、実際に手を動かすことが大事です。『英文法基礎10題ドリル』は、並べ替えの英作文演習を通して、文のカタマリや仕組みを理解することができます。『英文解釈の技術100』は、英文のSVOCを取りながら日本語訳をつくり、解答解説と比べながら英文の理解の仕方を学習できます。これらの教材を高2の3月までに進めると、高3でよいスタートを切れるはずです。
文構造が取れるようになったら、長文読解の問題集に進みましょう。特に『全レベル問題集(共通テストレベル~私大標準レベル)』は、全ての文に対して文構造が書かれているので、自分が考えていた文構造や意味が正しいかどうかを確認しやすいので、お勧めです。共通テスト~標準的な私大レベルを高3の1学期~遅くとも高3の夏休みには取り組みましょう。「文構造がとれているかどうか」や「もう長文の演習に入ってよいか」は、自分では判断が難しい部分ですが、毎回授業で見ている指導者であれば正確な判断ができます。これも家庭教師のメリットといえるでしょう。
3 標準的な入試問題の英文は読めるが、難関大学(早慶等)レベルの読解に苦戦している方(模試の偏差値60以上)
文構造が取れ、語彙も単語帳一冊は入っている状態でも、早慶等の難関大学の英文は読めないということは多々あります。難関大学の入試が要求するレベルは、現在とても高くなっています。これに対応するには、語彙や背景知識・教養といった「読み方」以外の要素が必要です。また、難関大学特有の出題形式に適応する必要もあります。
語彙の増強には『速読英単語上級編』や『リンガメタリカ』(いずれもZ会)などの単語帳を使いましょう。特に『リンガメタリカ』は、話題別の文章を読み、その文脈で単語を覚えられるものとなっていますから、読解としても語彙の増強としてもお勧めです。背景知識がある方が読める文章は多いですから、こういった学習も取り入れてみましょう。これは高3の夏休み~2学期いっぱいを使い、できるだけ反復して定着させましょう。もちろん、語彙の増強に終わりはありません。「解いた長文に出てきた語彙は覚える」習慣をつけるとさらに良いでしょう。また、早慶等の一部難関大では会話表現の難易度も高いです。『システム英熟語』(駿台文庫)を活用することも効果的です。
出題形式別の解法については『英語長文出題パターン別演習(標準~やや難レベル)』(河合出版)から始めましょう。空所補充や傍線解釈等、典型的な出題形式の解法が詳しく解説されていますから、「解き方」を練習するのに最適です。高3の1学期~夏休みには一通り解きましょう。これらを終えたら、『合格へ導く英語長文Rise読解演習(最難関編)』などで読解トレーニングを行いましょう。
高3の2学期以降、志望大学の形式に近い問題がない場合は、古本屋などで以前の過去問を手に入れ進めることも有益です。この場合、赤本の解答解説で分からないこともあると思います。ここでも家庭教師が有効活用できます。過去問を解く→解答解説を読む→それでも分からない部分を家庭教師に解説してもらう→類題を探してもらい解く、というような過程を踏むと、難関大に合わせたレベルの演習を重ねることができるのです。
段階的な学習が大切
長文読解は、語彙力や文法力の総合的な能力が必要です。そのため、読解能力の向上にはある程度の時間がかかります。高1・高2から段階的に学習することが望ましいですが、受験学年まで苦手が続いていた方は、上述のような家庭教師のピンポイント指導で挽回を図りましょう。