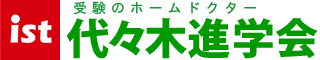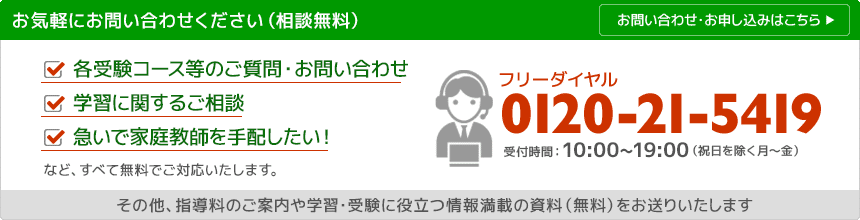大学受験の古典とは
高校古典では、「言語文化の享受」と「古典に親しむ」を学びの目的としています。先生が古典を読み解き、そこに書かれた内容を味わい、古典時代の人と現代人との共通点・相違点について考えていく、そうした「鑑賞」が、高校授業の主眼となるわけです。
一方、大学受験では、「初見の文章を読み、内容を掴む力」が問われます。当然、誰にも教わっていない文章を自力で訳せなければ、話は始まりません。そのためには語彙を覚え、文の構造を捉え、内容を掴んでいかなければなりません。こうした語学としての「解釈」が、受験古典の主眼です。
受験に向けて学ばねばならないこと
「受験古典」を突破するため、まず皆さんが取り組まなければならないことは、以下の3点です。
1 単語・文法を覚える
基本となる重要単語、重要文法を知っている必要があります。単語は、単語帳での学習が効果的ですが、文章に出てきた知らない単語の意味を確認する作業も怠らないでください。文法については、用言・助動詞・助詞・敬語などの意味用法・訳し方を知らなければなりません。口語訳問題では、文法事項の知識をベースにして訳すことが求められます。また文法識別という形で、単独の文法問題が出題される場合もあります。
2 緻密な全訳ではなく大意をつかむ
現実問題として、辞書を引かずに古典を緻密に全訳するのは困難です。むしろ文章の大意を掴む練習をする方が現実的です。日本語は、文末で大事なことを述べる言語なので、句読点で切れる固まりの末尾の語意を中心に、文意の核を掴みましょう。その上で、「誰が(主体)」「誰に・何を(客体)」「なぜ(原因理由)」「どうした(述部)」を探していけば、何を言っているかが見えてくるはずです。特に原因理由には注意しましょう。原因理由を意識すれば、文脈も掴め、主語も見えてくることが多いです。
3 選択肢の切り方のトレーニング
中上位レベルまでの大学や共通テストでは、客観式(選択肢)の出題形式が基本です。客観式の設問を解く際は、前後の流れから答えを選ぶのではなく、まずは傍線部中の重要語を探して、語彙的に正しいものを選びましょう。それでも解らない場合は、一文中の修飾関係、因果や対比といった傍線前後の論理関係…という順に意味を確認していくとよいでしょう。
難関大に向けての具体的取り組み
また、より高いレベルの大学を目指していく場合は、次のような取り組みも必要になります。
1 古典時代の文化・思想を学ぶ
古典の時代には、現代とは異なる常識があります。「平安時代の貴族は、普通こう考える」、「仏教思想の時代なら、これが常識である」といった、文化・思想をベースにした考え方を知っておくと、難度の高い文章を読む際に役立ちます。また、超頻出出典の著者の基本思考を知っておくと、読解が楽になります。例えば、江戸時代の国学者、本居宣長の文章では、基本「儒教・仏教・中国の文化」が批判され、人間の「真情」に基づく思考を肯定する等は、知っておいて欲しい知識です。
2 記述対策
主に国公立大においては、記述の解釈問題、説明問題が出題されます。正確に訳す技術、直訳を自然な言い方に言い換える技術、理由や意味を説明する技術が求められます。記述の基本的な書き方を学ぶとともに、自分の書いた記述解答を添削してもらい、完成答案を作れるよう練習しましょう。
3 漢文対策
共通テスト・国公立二次・早稲田大などでは、無視できない配点量で漢文が出題されます。国立や最難関私大を目指す受験生は、必ず漢文の対策をしてください。まずは、基本句形・重要語句と漢文構造の基礎を確認しましょう。句形・重要語句は、参考書・教科書等に載っているものを覚えます。また、漢文の構造においては、述語の前に主語や助動詞・副詞、後に目的語が来るのが基本です。述語の前の漢字を目的語と取ったり、述語の後の漢字を副詞と取って訳している選択肢を選ばないことです。そして、漢文でも古文と同様に、定番の思想・常識があります。特に、儒家思想・老荘思想・法家思想は覚えておくべきです。
受験に向けてのステップとおすすめの参考書
上記の学習をスムーズに進めていくためには、次のような段階を踏んで、学習を完成させていく必要があります。おすすめの参考書とともにまとめます。
1 高2〜夏期前半
まずは、300語〜800語程度の古文単語を覚えていきましょう。単語帳は、語源解説が載っているものが良いです。『Key&Point古文単語330』(いいずな書店)など、学校で採用されているもので問題ありません。古典文法は、「接続」の概念を踏まえた上で、一学期のうちに頻出の助動詞・助詞等の訳し方を一通り確認しておきましょう。学校で配られる文法の教科書では、意味の区別法が載っていないので、『古典文法基礎ドリル』(河合出版)など、区別法が載っているものを一冊仕上げると良いです。並行して、教科書に載っている短めで定番の文章を使って、訳の練習をしましょう。典型的な論展開、主張パターンを知っておくことは、今後の読解の手助けになります。
2 夏期後半〜二学期
敬語法についても、少なくとも夏までに確認しましょう。敬語がわかると、省略された主語目的語の区別がしやすくなります。単語文法知識がある程度頭に入ったら、基本的な問題集などを用いて、アウトプットの練習を積んでいきましょう。『古文上達基礎』(Z会)は、読解力をつけながら文法の基本が確認できる良書です。こうした練習問題を通じて、「に」の識別・「ぬ・ね」の識別等の文法識別についても、確認していきましょう。
漢文が必要な受験生は、夏までに基本句形と頻出の漢字についてまとめておくべきです。漢文が苦手な受験生は『漢文ヤマのヤマ』(学研)などから勉強していきましょう。文章題については、有名な古事成語・ことわざの由来となったエピソードを読んでおくことをおすすめします。
3 漢文対策
二学期前半に引き続き、徐々に長い文章・難しい文章の問題集をこなしていきましょう。無理に全訳せず、大意をつかんで設問を解いていってください。また、時間配分と出題傾向を確認するため、過去問に取りかかるのもこの時期です。文学史の有無・文法問題の有無・特殊な出題傾向かどうか(明治文語文等)などの出題傾向を過去問で必ず確認し、対策を講じてください。
4 直前期
直前期は原点に戻り、基本文法・基本単語・文学史・読解問題の復習など、基礎のチェックを中心に学習をすすめましょう。過去問を直前期に解くのはあまりおすすめしません。近年の過去問は、「最も出る確率の低い問題」と言えます。それを解くことに時間を割くのはムダが多いです。また、解けなくて落ち込む危険性もあります。新しいことをやるより、過去に学んだことを固め、本番で落とさないようにすることが大事です。現代文の学習法同様、冬期までに合格への目処がつくよう、学習計画を立てる必要があります。受験勉強のスタートは早めに切りましょう。
家庭教師の活用法
以上の学習を進めていく上で、家庭教師は、次の点で有効な選択肢となります。検討をおすすめします。
1 無駄のない学習計画が立てられる
古典を学ぶ上で、古文文法や漢文句形の知識は必須のものとなります。ですが、高校での扱いにはばらつきもあり、塾・予備校でも「すべての文法句形を丁寧に扱うクラス」と「文法句形を項目立てず、読解の学習をするクラス」の両極になりがちです。家庭教師であれば、受講生の実情に合わせ、効率的に知識・技術をまとめることができます。
2 読解法・設問解法が学べる
高校の授業は、作品そのものの鑑賞が中心になるため、入試に即決した読解法・設問解法を学べない場合があります。家庭教師であれば、点数に直結する説明を、あなたのレベルに合わせて受けることができます。
3 志望校に合わせた対策ができる
漢文の有無、文法文学史の出題率、明治文語文の出題等、古典は現代文以上に、大学ごとに傾向の違いが見られます。家庭教師であれば、あなたに合わせた学習プランを組むことができます。